小学生でもわかる!「代謝」のお話、基本のキ

代謝がいいと痩せやすいとか、代謝が悪いと冷え性になると聞きますが、そもそも「代謝」ってなに?とにかく簡単にご説明します!
細胞が入れ替わること、それが「代謝」!
人間には約60兆個の細胞があると言われています。
この細胞が色々な臓器をつくり、異なった機能を持っています。
細胞ひとつひとつは、それぞれ大きさ、素材(組織)も異なっていますが、全体を組み合わせて、私たちは、生命を維持しています。
そして、この細胞はずっと同じものを使っているわけではなく、日々更新、新しいものに入れ替わっています。
このことを、「代謝」と言います。
代謝にも種類がある!「異化」と「同化」
異化とはエネルギーを引き出す反応のこと
わかりやすく、簡単に説明すると、食べ物(大きな分子)を食べた後、食べ物は、消化分解されます。すると、大きな分子は小さな分子に変換されますが、その過程で得られるエネルギー(ATP)を引き出す反応のことを異化と言います。
ATPとは、アデノシン3リン酸のことですが、生命を維持するためにとっても重要なエネルギー源になります。
このワードについては、次回以降、このブログで簡単にご説明しますので、またチェックしてくださいね。
同化とは、エネルギーを使って身体を成長させること
同化とは、異化の反対で、エネルギーと小さな分子を使って、大きな分子に変換することです。
たんぱく質は、体内で小さな分子であるアミノ酸に変換(異化)されますが、体内の各組織で、再び再合成されて、体の細胞として生まれ変わります。
簡単に言うと、食べたお肉(たんぱく質)から変換されたアミノ酸が筋肉をつくることを、同化と言います。
代謝の速度は細胞によって異なる! 代謝が悪いとデメリットがあるの?
皮膚の代謝は、一ヶ月ほどです。
皮膚の一番奥にある細胞が二つに分裂、皮膚表面まで上がってきます。
約28日で皮膚の表面から垢として剥がれ落ちます。
新しい皮膚に入れ替わらないと、肌のくすみや、シミの原因になることもあります。
胃の粘膜の代謝は、なんと1~2日!
しかし、年齢とともに、代謝が低下してくると、胃が消化吸収する範囲が減ってきてしまうそうです。
これが、加齢による、消化不良や悪酔いの原因になることもあります。
骨の細胞は、一年間に20~30%入れ替わります。(骨のリモデリング)
骨量は20代でピーク、その後は安定していますが、40代以降は、骨量が減っていきます。
骨のリモデリング(代謝)のイメージ
出典:アステラス製薬
代謝の良し悪しは、腸内環境が決め手!
それでは、代謝を良くするためには、どうしたらいいのか…
その解決のヒントとなるのが、腸内環境です。
腸内には約100兆個もの細菌がいると言われています。その中に、代謝を良くしたり、ダイエットに効果的な、短鎖脂肪酸(たんさしぼうさん)を作ることができる細菌がいるのだそう!
この細菌のエネルギー源として必要なのが、水溶性食物繊維です。
水溶性食物繊維を多く含む食品の一例は以下の通りです。
■海藻類 ・ひじき・めかぶ・わかめ・もずく など
■果物類 ・キウイ・バナナ・りんご・かき・いちご など
■野菜類 ・ゴボウ・アボカド・オクラ など
■豆類 ・納豆・きなこ
こういった食品を摂取することで、腸内細菌の働きが活発になり、代謝をよくする短鎖脂肪酸を増やすことができると言えそうです。
いかがでしたか?
代謝や、それにまつわるお話は、これからシリーズでお伝えしていきますので、お楽しみに!
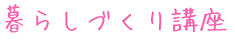
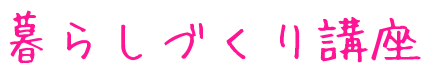


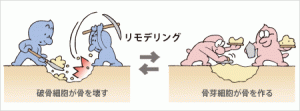
























この記事へのコメントはありません。